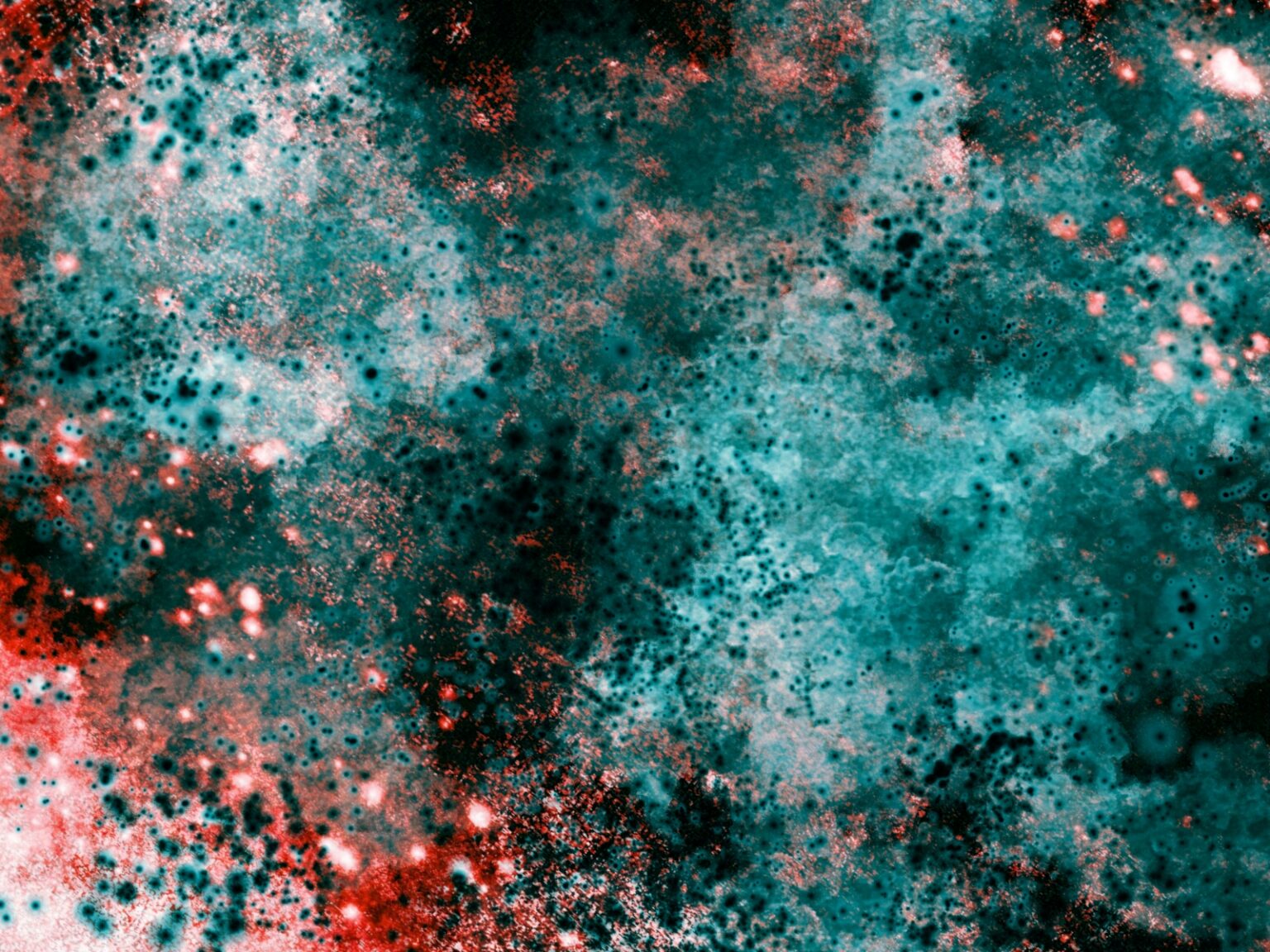作品概要
王谷晶『ババヤガの夜』(河出書房新社、2020年10月)。
喧嘩の腕を買われ、関東有数規模の暴力団・内樹會に雇われた新道依子。常に血の匂いが漂うような毎日の中、運転手兼護衛として会長の娘・尚子と接するうちに、2人の間に名前のつけられない関係性ができていく。
2025年7月、英訳版 The Night of Baba Yaga(サム・ベット訳、Harvill Secker)が、英国推理作家協会(CWA)のダガー賞翻訳部門を受賞。
→ ソース:朝日新聞デジタル「王谷晶さんの小説、CWA賞受賞」2025年7月3日
身体感覚としての読書体験という二律背反
読者自身の身体が登場人物の身体に同調する体験
ダガー賞翻訳部門の受賞で話題となった王谷晶さんの『ババヤガの夜』は、圧倒的な没入感が出色の小説です。通常、このような没入感は一人称の語りによる小説で強く感じられるもの。しかし本作は三人称による客観的な視点から描かれているにも関わらず、新道依子の拳の当たる音が聞こえ、血の匂いが漂い、自分が依子の肉体と同じ痛みを受けているかのような身体的な臨場感があるのです。これは、なぜなのでしょうか。
喧嘩経験がなくても痛みを「感じる」
私自身に依子のような喧嘩の経験はありません。他人と拳を交わしたこともなく、自分の拳によって流れた他人の血の匂いを嗅いだこともないのです。それなのに、この小説を読んでいると、自分の身体が依子の身体に同調するような感覚がありました。
王谷さんはダガー賞受賞後の記者会見で「テキストでアクションをやりたいということが最初にあった」と語っています。映画のようだ、漫画のようだと評されることが多い本作は、イメージを喚起する力が群を抜いていることは議論の余地がないでしょう。
しかし、私は受動的にスクリーンを眺めるような体験とは本作の読書体験は異なると思います。主人公の身体に読者の身体が同調するような圧倒的な没入感こそが、本作の特筆すべき点ではないでしょうか。そしてこの没入感が三人称の語りで実現されていることは、他に類を見ない本作の個性だと思います。
→ ソース:朝日新聞・Book.asahi.com「王谷晶さん、ダガー賞の受賞後に語った「暴力的な物語を書く責任」」(2025年7月5日)
メルロ=ポンティ的な「身体を通じた世界把握」
モーリス・メルロ=ポンティは『知覚の現象学』(滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1967年)で「人間は身体を通して世界を知覚する」と主張しました。単なる物質的な身体ではなく、環境と相互作用する主体的な存在である「現象的身体」を重視したのです。
本作の世界を、読者は依子の身体を通じて創設するように錯覚する―そのような読書体験が生まれる仕掛けが本作にはあるのではないでしょうか。
ババヤガが象徴する「誰かの何か」ではない身体
ババヤガ=鬼婆という理想
本作のタイトルにある「ババヤガ」はスラブ民話に登場する妖婆・鬼婆。依子の祖母が語るおとぎ話に登場し、依子と尚子が憧れる理想像として象徴的に語られます。
→ ソース:ハフポスト日本版インタビュー(2021年2月15日)
お仕着せのアイデンティティを超克する―「誰かの何か」ではないものとしてのババヤガ
王谷さんは同インタビューで「世間から刷り込まれたイメージや価値観を、『これが自分』と内面化してしまうことってありますよね。誰しもが内面化しがちなものを、吹き飛ばすような、力技で剥ぎ取っていく。そんな部分もこの小説で描けたらと思いました」と語っています。
王谷さんは、依子の身体描写においては「重量感」を意識したとする一方、顔立ちや美醜、体型といった容姿の詳細は意図的に避けたとのことでした。つまり、依子の肉体の質感を重点的に描きながらも、「女性らしさ」というお仕着せのアイデンティティに関わる部分は徹底的にそぎ落としたのです。このように計算され尽くした描写に、本作の秘密があるのではないでしょうか。
「誰かの何かとして生きるのは無理」。これは本作で最も印象的な言葉の一つです。他者から押し付けられたアイデンティティを超克するもの―それこそが依子と尚子の理想、ババヤガなのかもしれません。
→ ソース:ハフポスト日本版インタビュー(2021年2月15日)
シスターフッドを超えて
「シスターフッドの物語」というラベルへの違和感
本作は、多くの記事で「シスターフッドの物語」と評されています。しかし、私は依子と尚子の関係に名前をつけたくない、ラベリングしたくないという気持ちがぬぐえません。「誰かの何か」ではない自分として生きること、ババヤガを理想とする2人の関係を「女同士の関係」として規定したくないのです。
登場人物の関係は型に収まらない流動的なもの
依子と尚子のおかれた状況を考えれば、それは「自由」とはほど遠いものだったかもしれません。けれども、二人の関係性はとても流動的で、「お嬢様と護衛」「親友」「姉妹」という型に収まるものではないと思います。ただ一つ、ババヤガへの憧れだけを共有する2人――。
ババヤガ―ジェンダー規範から逸脱する身体性の象徴
ジュディス・バトラーは『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(竹村和子訳、青土社、1999年)で、ジェンダーとは固定された本質的なものではなく、特定の行為や振る舞いを繰り返し演じることによって、その都度構築されるものだと述べています。彼女は、異性愛を前提とした性別体制を「抑圧」とみなし、それに抵抗する身体的実践を重視しました。
本作が受賞したダガー賞は、優れた犯罪小説やミステリーに与えられる賞です。本作の叙述トリックの根底には、「ババヤガ=鬼婆」に対する依子と尚子の希求、そしてジェンダー規範に抵抗するパフォーマティブな実践があるのではないでしょうか。
この他者から付与されたアイデンティティへの抵抗は、特別なことではありません。これは、私が私であるために日常的に実践していることでもあるのです。「誰かの何かとして生きるのは無理」とは依子の叫びであると同時に、私自身の叫びでもある――本作の没入感は、依子と尚子の希求するものが私の求めるものとも重なり合うからこそ生まれるのかもしれません。
結論
- 『ババヤガの夜』は、主人公が「誰かの何か」ではないアイデンティティを求める身体の実践を描いた作品で、その実践が読者の身体を巻き込み、圧倒的な没入感を生み出しています。
- ババヤガというアイデンティティを獲得しようとする実践が内包するのは、社会的規範を揺さぶる力――文学が身体を通じて読者に問いかける可能性示す、唯一無二の作品だと思いました。
- この作品は、身体的な臨場感を伴う読書体験をもたらしてくれる、稀有なエンターテイメントです。
参考文献・ソース一覧
- 王谷晶『ババヤガの夜』河出書房新社、2020年10月
- The Night of Baba Yaga(Sam Bett 訳、Harvill Secker、2025年)
- 朝日新聞デジタル「王谷晶さんの小説、CWA賞受賞」2025年7月3日
- 朝日新聞・Book.asahi.com「王谷晶さん、ダガー賞の受賞後に語った「暴力的な物語を書く責任」」(2025年7月5日)
- 朝日新聞 Book.asahi.com「王谷晶『ババヤガの夜』レビュー」2022年3月1日
- ハフポスト日本版「王谷晶さんインタビュー」2021年2月15日
- モーリス・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1967年
- ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデンティティの攪乱』竹村和子訳、青土社、1999年
📚 関連書籍(準備中)
- 王谷晶『ババヤガの夜』単行本(河出書房新社、2020年)
- 王谷晶『ババヤガの夜』文庫本(河出文庫、2023年)
- The Night of Baba Yaga(Sam Bett 訳、Harvill Secker、2025年)
- モーリス・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』新装版(法政大学出版局〈叢書・ウニベルシタス〉、2009年)
- モーリス・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』改装版(法政大学出版局〈叢書・ウニベルシタス〉、2015年)
- ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』新版(竹村和子訳、青土社、2021年)
- ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』(竹村和子訳、青土社、1999年 初版)
※Amazonアフィリエイトリンクは承認後に追加予定です。

言語・文芸・仕事・子育てをテーマにした「ふみの森:学び・文芸・仕事|晴耕雨読の書評ブログ」を運営。大学受験指導(英語・国語・日本史)、および外資系コンサルティング会社での経理財務領域の業務改革・システム導入で培った経験を活かし、正確なリサーチとわかりやすい構成を心がけています。取り扱う分野は、英文読解・読書術・ライフハック・国際協業など。業務委託に関するご相談や記事制作のご依頼、具体的なお見積り依頼も承っております。